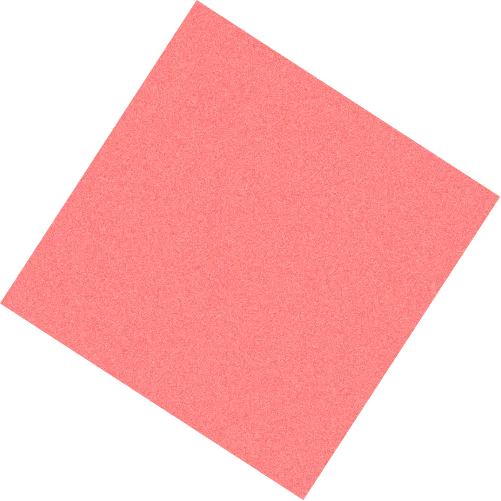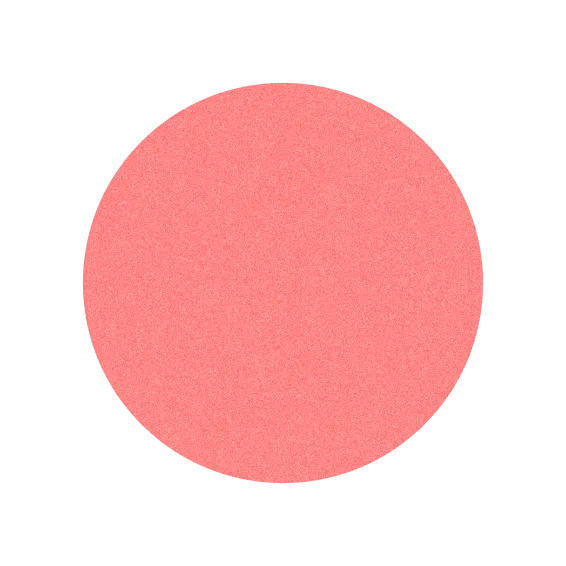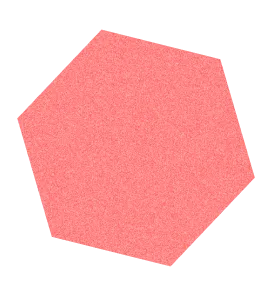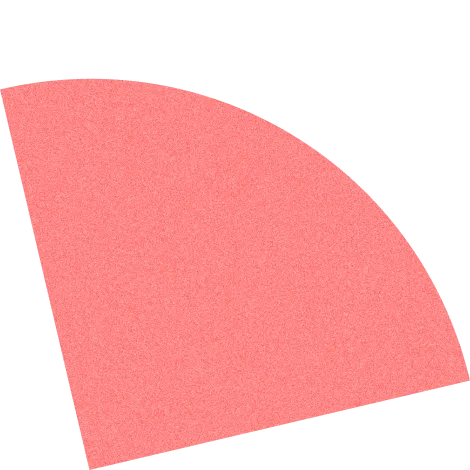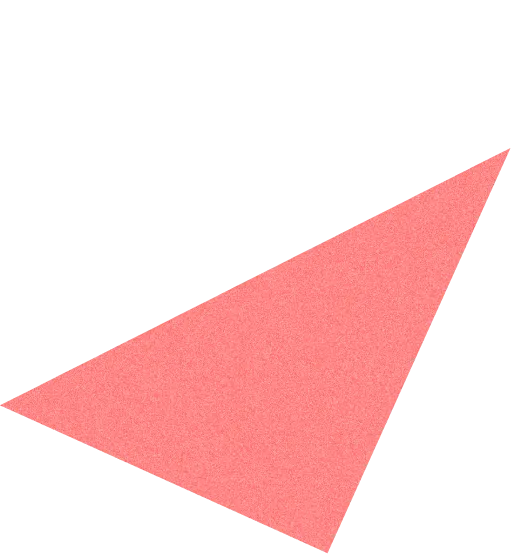「そろそろ、ITをわかりやすく。」をモットーに受託開発を行ってきたIT企業「Fabeee」。
「モノづくりの楽しさを忘れて欲しくない」という思いからプロジェクトを一括管理できるツールを自社開発。そこから業務を効率化させることで、クリエティブな発想を生み出す時間を提供したいと「ALICE構想」を打ち出したFabeee株式会社取締役CTOの杉森さん。
前編では受託開発の課題、自社開発ツール「EPQOT」、情報を会社の資産として活用するエコシステム「ALICE構想」についてお話を伺いましたが、後編となる今回はエコシステムを社内に根付かせるために発足された「Imagineering STUDIOS」について、そこから描かれるFabeeeの未来についてお話を伺いました。
お話を伺ったのは……
Fabeee株式会社 取締役 CTO
杉森 由政(Yoshimasa Sugimori)
東京理科大学在学中に宇宙物理学を専攻。線形代数、統計解析やテンソル計算といった機械学習の基礎知識を習得。2016年よりシステム会社のエンジニアとして就業。行政システムやSNSサービス、ゲーム開発等、短期間で様々なカテゴリーの開発に従事。2017年よりFabeee株式会社に入社。Pythonを用いたIoTプラットフォームの設計開発はもちろん、機械学習・ディープラーニング分野のプラットフォーム開発をリード。2018年2月同社CTOに就任。就任後は、AIの分野でシェアNo.1を目指すというビジョンを掲げ、現在、広島大学との連携研究において、生体データを解析。
――――
<目次>
■「Imagineering STUDIOS」誕生の経緯
■マーケティングは二の次!?「Imagineering STUDIOS」の由来について
■「モノづくりの楽しさを失わず、ビジネスにつなげる方法」はきっと存在する
■「Imagineering STUDIOS」のこれから
■Fabeeeが想像する「境界線のない世界」
――――
■「Imagineering STUDIOS」誕生の経緯
──これまで多くの受託開発を請け負ってきたFabeeeにとって「受託開発ではない、自社開発」はどんな意味合いを持ちますか?
杉森:自社開発は会社にバリエーションをつけるもの、上場のための布石だと捉えています。「Fabeeeといえばコレ」というプロダクトをつくって「らしさ」を生み出せないと、会社にバリエーションがつきません。上場を目指すなら自社開発は必ずやるべきことだと思っています。
──企業としての色をつけていくわけですね。
杉森:そうですね。じゃあ「Fabeeeらしいってどういうこと?」と考えたとき、「ALICE」というフレームワークを活用するエコシステムが思い浮かびました。この仕組みを会社の文化として組み込み、実践していくことがFabeeeらしさにつながるのではないかと。
──「ALICE」は業務を効率化させ、クリエイティブな発想を生み出す時間を提供する仕組みのことでしたよね。
杉森:はい。この仕組みを社内全体に主導的に進めていけたらいいなと思っていて。ただ企業文化にするには説明だけじゃ難しく、誰か引っ張っていく人が必要でした。例えば文化になっても浸透を担う人間がいないと、文化にはならない。いちばん最初の歯車を回す部隊みたいなものをつくらねばと立ち上げたのが「Imagineering STUDIOS」という組織だったんです。
■マーケティングは二の次!?「Imagineering STUDIOS」の由来について
──文化浸透のための組織!名前を「Imagineering STUDIOS」にしたのはなぜですか?
杉森:ディズニーのテーマパークをつくるエンジニアたちのことを「イマジニア」というんですね。これはウォルト・ディズニーが「想像を技術力で実現する」という意味合いで生んだ造語らしくて。僕らがやりたいことも似ています。偏った着想に縛られず、まずは自由に発想する。そしてそれが社会にどんな良い効果をもたらすかを考える。
──自由な発想……。市場調査よりも、発想が先にくるんですか?
杉森:そうです。「市場でこんなものが求められているから、これつくったら絶対売れるよね」ではなくて「これあったら面白そう」からスタートする。マーケティングはそのあとです。あとから「〇〇で困っている人には、こんな使い方をしたらいいかも」と意義を見出してプロダクト化したい。そんな理由でイマジニアリングと付けました。

■「モノづくりの楽しさを失わず、ビジネスにつなげる方法」はきっと存在する
──開発はマーケティングありきだと思っていたので、なんだか新鮮です。
杉森:つくりたくないものをつくる。それもビジネスの在り方のひとつです。ただ「モノづくりって楽しい」とみんな感じたことがあると思う。その気持ちを大事にしながら、ビジネスにつなげる方法は本当にないのだろうか?と思っていて。それならマーケティングから開発ではなく、開発からマーケティングする順番が適しているんじゃないかと。
──杉森さんは「モノづくりの楽しさ」と「何にもとらわれない自由な発想」を大切にされているんですね。
杉森:良いアイデアなのに「それ多分売れないよ。つくらなくていいよ」となるのは、もったいない。良いアイデアならまず形にして、そのあとどうビジネスにするか全員で出し合おうぜ!のほうが気持ちいいなって。
──ビジネスなので現実的な厳しさもありそうですが、その考えに共感される方は多そうです……!
杉森:技術的な興味や好奇心のひらめきひとつあれば、たくさんのメンバーのアイデアでビジネスに変えていけると真面目に思っていて。それほど難しいことだとは思っていない。企業としてFabeeが成功事例になるといいな、と期待してます(笑)
■「Imagineering STUDIOS」のこれから
──「Imagineering STUDIOS」の今後の展開について教えてください。まずは短期的なところから。
杉森:今は僕1人なので、まずは社内でのメンバー集めです。文化の牽引や中心を担うので、ビジョンやバリューを再現できる人物で最初は固めたいなと思っています。
──「Imagineering STUDIOS」メンバーに入るのに、どんな条件がありますか?
杉森:まずはFabeeeを好きでいてくれること。それから現場でどんな課題があり、どう解決すれば業務効率化につながるか?そんな課題感を持てる人。入社後すぐに「Imagineering STUDIOS」メンバーに採用することは基本的に考えてなくて。どんなに優秀な人でも現場でいろんな課題やコミュニケーションを経験してから。直接アサインではなく現場や上長からの推薦でメンバーを集めていくつもりです。
──メンバーを集めたあとは、どんなことをしていきますか?
杉森:いずれはFabeeeに根付いた文化を外に向けて発信したいと考えていますが、社外に文化を発信するにはFabeeeメンバー全員が「この文化、めちゃめちゃいいよね」と良さが分かっていないとダメ。だからビジョンやバリューを分かりやすく、深く理解してもらうために社内ワークショップなども行っていきます。
──どんな内容になりますか?
杉森さん:実は先日行いました。謎解きゲームです。
──謎解き……⁉
杉森:問題を解いていくと「EPQOT(Fabeeeの自社開発ツール)」のWikiページに飛びます。そのテキストにキーワードがちりばめられていて、それがビジョンやバリューになっているんです。ひとつずつ拾っていくと最終的に謎が解けるようになっています。
──楽しみながらビジョンやバリューが学べるんですね。
杉森:ビジョンやバリューは、分かりやすく親しみを持ってもらったほうが理解されやすいかなと。ということで2021年は社内の文化の消化・浸透に注力していくつもりです。
──来年以降に向け、中期的な目標はありますか?
杉森:「Imagineering STUDIOS」はエコシステムの仕組みを社内に浸透させるだけでなく、会社の未来も見据え「新規事業開発室」という側面を持っています。中期的には自社プロダクトを中心に、新規プロジェクトも計画予定です。
──どんなプロダクトをつくるか、構想はすでにありますか?
杉森:組織に応じて人が持つ価値や才能を適材適所で使えたり、パフォーマンスを最大限に発揮できたりするような仕組み提供するプロダクトを考えています。プロダクトが事業化したときに「Imagineering STUDIOS」出身メンバーが中心になっていたらいいなとも思いますね。事業責任者や開発のリードになったりすれば、文化浸透にも紐づきます。上場を目指すなら会社にバリエーションをつける必要があるので、自社プロダクト開発は重要視しています。
──受託からの脱却ですね。
杉森:そうですね。上場に関しても、どれくらいでできるかは「Imagineering STUDIOS」の努力次第かと思っています。
■Fabeeeが想像する「境界線のない世界」
──では最後に、Fabeeeが描く未来があれば教えてください。
杉森:「ALICE」による業務効率化の究極形態はコードじゃない。僕らがこれからやっていこうとしている取り組みの究極形態は「何でもできる世界」です。
──なんでもできる世界?
杉森:やりたいことがすべてできてしまう世界です。例えば3Dプリンターと連携すれば欲しいと思ったものがリアルに目の前に現れますよね。インターネットを介せば現実にやりたいと思ったことができる。それは技術者だけの特権ではなく、すべての人ができることです。できることが当たり前になった瞬間、オンラインとオフラインの境界のない世界が広がる気がしています。
──非エンジニアでも、欲しいと思ったものを手にできる世界……。
杉森さん:僕らは開発というアプローチから始まっているので、まずはシステムです。ただアウトプットは何でもいい。いろんなことができるようになって、すべてが連携していけばインターネットを経由して何かをすることに変わっていく。オンラインとオフラインの境界線がなくなる。それがFabeeeのビジョンになっていると思います。
──「Imagineering STUDIOS」を立ち上げて社内に文化を根付かせ、チャレンジ・アップデートを繰り返し、課題を解決していった先にオンラインとオフラインのない世界が来る?
杉森さん:課題は同じアプローチで解決できるものの、ブラッシュアップし続けることで長期的なビジョン達成につながることが「ALICE構想」の全体像なのかもしれません。「境界線のない世界」は僕らのゴールではなく、取り組みを続けていった先の究極形態、当然そうなっていく世界なんです。Fabeeは最初から、その未来を目指していきたいなと思っています。
※本記事は、ForbesJapan Careerに掲載された記事をリブログしたものです。
https://forbesjapan-career.com/story/303
専門的な要素が多いことから「分かる人にしか分からない分野」といわれるIT業界。そんな世界で「そろそろ、ITをわかりやすく。」をモットーに活動しているFabeee株式会社。「伝わらない専門用語をまくしたてるコミュニケーションには愛がない」とし、IT技術をすべての人が理解できるよう「伝える力」の重要性を説きながらDX、リモート開発支援など数多くの受託開発を扱ってきました。
受託開発は工程が決められた開発手法で進めるケースが多く、綿密な計画のもと実行していくことが可能です。ただ決められた要件内での作業は自由度が低く、クリエイティブな発想が生まれにくいこともあります。取締役CTOの杉森さんはそんな開発業務に対し、ある課題を感じていたそうです。
今回は課題解決への思い、自社開発ツールの全容、ツールを用いることで実現可能となった「ALICE構想」についてお話を伺ってきました。
お話を伺ったのは……

Fabeee株式会社 取締役 CTO
杉森 由政(Yoshimasa Sugimori)
東京理科大学在学中に宇宙物理学を専攻。線形代数、統計解析やテンソル計算といった機械学習の基礎知識を習得。2016年よりシステム会社のエンジニアとして就業。行政システムやSNSサービス、ゲーム開発等、短期間で様々なカテゴリーの開発に従事。2017年よりFabeee株式会社に入社。Pythonを用いたIoTプラットフォームの設計開発はもちろん、機械学習・ディープラーニング分野のプラットフォーム開発をリード。2018年2月同社CTOに就任。就任後は、AIの分野でシェアNo.1を目指すというビジョンを掲げ、現在、広島大学との連携研究において、生体データを解析。
――――
<目次>
■受託開発の課題「業務効率化」は売り上げのためじゃない?
■「モノづくりの楽しさを忘れて欲しくない」から始まった自社開発
■NO属人化!情報を会社の資産として活用するエコシステム
■プロジェクトをまるっと一括管理できる「EPQOT」
■価値を最大限に再活用するためのエコシステム「ALICE」と自社開発ツール「EPQOT」の関係性
――――
■受託開発の課題「業務効率化」は、売り上げUPのためじゃない?
──「Fabeee」は今まで受託開発をメインにやってきた会社だと伺いました。
杉森:はい。企業の依頼に合わせ、システムやソフトウェアを開発してきました。
──受託開発を受けていく中で、課題に感じる部分があったそうですね。
杉森:はい。僕は業務を効率化させたくて。受託に限らず、開発業務。ひいてはほかの部署もそうです。Fabeeeメンバー全員の仕事の負担を減らしたいと思っていました。
──それは……生産性を上げて、売り上げを伸ばすためですか?
杉森:結果的にそうなれば嬉しいですが、業務効率化を目指したのは別に理由がありまして。
■「モノづくりの楽しさを忘れて欲しくない」から始まった自社開発
──別の理由?
杉森:はい。Fabeeeは開発屋として多くのシステム開発をしてきましたが、それは常に「しなければいけないタスク」に埋もれている状態でした。あるとき「この状況はモノづくりする人のあるべき姿なのか?」と疑問に感じて。ボトムから上がってくるアウトプットをプロダクトに昇華する。モノをつくることが楽しいことだと認識する。そうやって自由にクリエイティブなことを考える時間がない状況に違和感を感じたんです。
──「やらなければならないこと」に終われて「やってみたいこと」を考える時間がない?
杉森:そうです。エンジニアはモノづくりに関わるのに、つくる楽しさを忘れてしまうのは不自由な気がしました。そこで業務を効率化して、余った時間を新しい発想を生み出す時間にすればいいと思ったんです。
──なるほど。
杉森:効率化のアイデアに役立ったのがGoogleが提唱していた「20%ルール」です。
──Googleの「20%ルール」は、仕事時間を分割したときに10割「やらなければいけないこと」をするのではなく、仕事の2割は未知の学びや視野を広げる取り組みをする時間に充てよう… というような習慣ですよね。
杉森:はい。「20%ルール」を適用するためには、どうしたらいいのか?それには今100%で取り組んでいる仕事を80%の時間でこなせるようになればいい。10時間かかる仕事を8時間で完成できれば、残り2時間は新しい発想を生み出す時間として提供できると考えたんです。

──とはいっても「100%の仕事を80%の時間でできるように」ってけっこう難しいですよね……?
杉森:もちろん100%の仕事に120%の時間がかかってしまう人もいます。若手は時間を要して当たり前だし、熟練者は80%といわずもっと早く終わることもあります。
──人によって仕事のスピードが違う……。
杉森:はい。業務が属人化しているんですね。なんとかできないかと思いながら効率化の仕組みや開発体制を考えていたら、ひとつのアイデアを思いつきました。
──おお!どんなアイデアですか?
杉森:考えたのはカスタムフレームワークやローコードの開発体勢です。例えば一度行った仕事を再度やると1回目より短い時間で終わることが多いですよね。それは効率的にできるようになったから。Aさんが行った案件と同じ案件をBさんが行ったらどうなるか。Aさんのやり方を知らないままだと属人化して人によってかかる時間は異なりますが、Aさんがやり方を共有していたらどうだろう?と思ったんです。
──やり方が共有されていれば、作業者が変わっても効率化される?
杉森:そう考えました。誰かの経験とやり方を会社の資産として活用する。そうすれば「この人がやるから早い」と属人化されず、自然に効率化されていくはずです。会社の資産として活用する仕組み、それをフレームワークに還元して開発効率を上げていく。そうした文化を社内につくりたいと思いました。
──「エンジニアが引き継ぎなく辞めてしまい、仕事に支障が出てしまった」といった話もよく聞きます。「経験を情報資産として社内活用」すれば、そんな属人化トラブルも少なくなるかもしれませんね。
杉森:行った仕事の価値を最大限に再活用する。この仕組みを上手く循環させている会社はほとんどないと思います。広い視野で見ればエンジニアも営業もバックオフィスも同じ仕組みを活用できるはずだし、成功例も失敗例もすべて情報資産として記録できるはず。行った仕事(価値)を最大限に再活用するためのエコシステム。これを僕は「ALICE構想」と呼んでいます。
■プロジェクトをまるっと一括管理できる「EPQOT」
──「ALICE構想」……!Fabeeeが自社開発したプロジェクト管理ツールは「EPQOT」だったと思いますが、「ALICE」と何か関係があるのでしょうか?
杉森:「ALICE」は仕組みのことです。対して「EPQOT」は自社開発したプロジェクト管理ツール。
──ふむふむ。……ここからなんだか難しい話になっていきそうな……(焦)
杉森:ではいったん「ALICE」は置いといて「EPQOT」についてお話ししますね。「EPQOT」はプロジェクト管理ツールとして開発したものです。
──管理ツールの種類には、Git系やガント・WBS系がありますよね。Gitはソースコードのバージョン管理が簡単にできるし、ガント・WBS系は各タスクとスケジュール全体が直感的に把握できる。「EPQOT」はどんな特徴を持つツールなのでしょう?
杉森:人によって使うツールはそれぞれかと思いますが、例えばBacklogだとGitのソースコードと紐付いた管理ができません。チケット管理はあるけどガント機能がなく、進捗管理に弱いところがある。FabeeeではGitとBacklogの両方を使っている人もいますね。なんとかひとつのツールでプロジェクト管理できないものか… と思い「ないなら自分でつくってしまおう!」と思ったわけです。
──(技術力を持つ人だけがいえる言葉……!)じゃあ、ツールのいいとこ取りをしたプロジェクト管理ツールが「EPQOT」ということになりますか?
杉森:そうだと思います。EPQOTはクライアントの業界、業種、機能、企業課題。課題からどんなシステム開発を行い、どう解決したか。案件の情報とソースコード、Git、タスクがすべて紐づいたプロジェクト管理ツールです。ひとつの案件で、誰がどのタスクをどのくらい時間をかけて行ったかもソースコードに紐づいたデータとして一括管理できる仕組みになっています。
──おお……。
杉森:困ったこと、解決できたことを記録する日報機能、それに対するコメント機能もあります。内容を確認しながらメンバー同士でコミュニケーションがとれますし、クライアント提供の資料もプロジェクトに紐付けて管理できます。チケット管理、ガント機能もありますね。
価値を最大限に再活用するためのエコシステム「ALICE」と自社開発ツール「EPQOT」の関係性
──そんな「EPQOT」と「ALICE」には、どんな関連があるんでしょう?
杉森:メンバーがデータマネジメントして「EPQOT」を使うと、データがどんどん変化します。そこにはソースコードに紐づいた業界業種の案件情報があります。「これで困った」「こんな方法で上手くいった!」という多様な情報を見せながら「もっと簡単に自走する仕組みにしよう」と「ALICE」にフィードバックするんです。
──フィードバックする……?
杉森:「EPQOT」にある程度情報が溜まると「ALICE」はその情報をもとに「より良い方法」をアップデートで生み出します。一度行った開発に似た案件の実装が必要なとき、「ALICE」がアップデートされていることでメンバーは前回よりも簡単に実装できるようになる、というわけです。
──すごい!
杉森さん:簡単にいうと「EPQOT」はインプット。「ALICE」はアウトプットする装置のようなものです。データを効率よく利用するためのアウトプットが「ALICE」なんです。
──なるほど!インプットとアウトプットの関係なんですね。
杉森:様々な案件をこなして新しいモノをつくっていけば、情報や課題をどんどん溜めていける。溜まったらまた「ALICE」をアップデートできる。好循環が生まれるんです。
──この仕組みを活用できれば自然に業務が効率化して、創造的な発想を生み出す時間もつくられるようになると……?
杉森:そうです!業務効率の改善、余剰時間を生み出すことにつながるかなと思います。
──なんだかすごい仕組みですね。杉森さんはこの仕組みを社内全体に浸透させたい、と考えているんですよね?
杉森さん:はい。「EPQOT」&「ALICE」の仕組みを、社内で「文化」として根付かせたいなと思っています。仕組みを文化に昇華させるには、最初の1回は啓蒙していく必要があります。正しい使い方を確立して、みんなにレクチャーする存在が必要です。そこで文化浸透を積極的に行うための「Imagineering STUDIOS」という部隊を立ち上げました。
<後編に続く>
後編では、プロジェクトチーム「Imagineering STUDIOS」についてお話を伺います!
※本記事は、ForbesJapan Careerに掲載された記事をリブログしたものです。
https://forbesjapan-career.com/story/302
「成功とは成功するまでやり続けること」──かの有名な松下幸之助氏の言葉だ。しかしながら多くの人は、一度大きな挫折を経験してしまうと、次の一歩を踏み出すのに臆病になるものである。
大半のスタートアップが夢叶わず破れていくこの世界ではなおさら、「自分には起業の才能がなかった」と諦め、人知れず舞台を降りてしまう起業家も少なくないだろう。
この記事で取り上げるのは、創業11年目にして今なお新たな挑戦を続けるFabeeeの創業者・佐々木淳氏だ。同社は「オンラインとオフラインの境界線のない世界を実現する」という大きなビジョンを掲げ、高い技術力を持ったエンジニアを組織して、企業のDX支援や技術開発を手がけている。
「何年後かはわからないけれど、車が空を飛び、人々がロボットと共存する未来は必ずやってくる。その時僕は、その世界の中心に居たいんです」。生き生きとそう語る佐々木氏の目は、真っ直ぐと未来の「成功」を見つめている。
ある時は中国でまさかの“裏切り”に遭って全てを失い、またある時は「これからプロダクトが伸びていくぞ!」というタイミングで突然サービス停止に追い込まれた。何度も挫折と絶望を味わいながら、なぜ諦めることなく新たな挑戦へと立ち向かっていけるのか? 11年分の“悔しさ”の物語について、佐々木氏と取締役CTOの杉森由政氏に伺った。
“会社が自然にぶっ壊れた瞬間”を、10年で2回見た
今年で創業12年目となるFabeeeは、企業へのエンジニア派遣やDX推進支援といった事業を中心に成長してきた。2021年現在、DX支援からITプロフェッショナルによる技術支援、経営層特化型AI研修プログラムなど、多角的に企業のデジタルシフトを支援している。取引先の企業規模は大小さまざまで、業界も不動産や金融から、オフィス家具メーカー、工場、そして行政まで幅広いという。
主要な提供サービス
| DX支援サービス「Fabeee DX」 |
|---|
| 初年度で累計20社、半期で黒字化。民間企業だけでなく行政とのプロジェクトや、ホワイトペーパーリリース後にエンタープライズ企業からのお問い合わせも増加 |
| リモート開発サービス「Fabeee Anyplace」 |
|---|
| コロナ禍が追い風となり取引社数が増加 |
| ITプロフェッショナルによる技術支援サービス「Fabeee Tech PARTNERS」 |
|---|
| 累計取引社数300社 |
さまざまな企業規模の競合がひしめくこの領域で同社が武器にしてきたのは、幅広い領域をカバーするハイレベルなエンジニア人材である。 Fabeee株式会社 代表取締役CEO 佐々木淳氏
Fabeee株式会社 代表取締役CEO 佐々木淳氏
佐々木
AIやブロックチェーンなどの先端技術については、それぞれの領域に特化したSIerが多い中、Fabeeeの強みはAIとブロックチェーン両方の領域でハイレベルなパフォーマンスを出せるエンジニアが揃っている点です。モノを作るうえで最も重要なのは、やはり人の部分が大きいと思っていて。最先端の技術を扱える優秀な人材を確保することには、力を入れています。
また、コンサルから開発、その後の保守・運用まで、シームレスに対応できる点も、組織としての強みなのではないかと思います。
しかしながら、ここで湧いてくるのは、「Fabeeeはどのようにして優秀なエンジニア人材を確保しているのか?」という疑問だ。ただでさえエンジニア人材が不足していると言われる中、AIやブロックチェーンなどの先端技術を扱えるエンジニアとなれば、大手企業からも引っ張りだこだろう。
この疑問に杉森氏は、「佐々木氏の描くビジョンに魅力を感じて入社する人が多い」と答える。 Fabeee株式会社 取締役 CTO 杉森由政氏
Fabeee株式会社 取締役 CTO 杉森由政氏
杉森
「オンラインとオフラインの境界線のない世界を実現する」というビジョンに共感して入ってきてくれる人が多いと感じます。なかなか抽象的なビジョンだとは思うのですが、要するに、一昔前から見たスマホのように、IoTを“技術”と意識せず、生活と一体化したモノとして自然に使う世界のことです。
その実現が加速していけば、やがてはSF映画の世界が現実になる。僕らはどのみちそんな未来が来るなら、今から取り組んでそこに向かっておこうと考えていて。その思想に共感する人たちが自然に集まってきてくれていますね。
佐々木の発想は、一見すると全く論理的じゃないんですよね。ただ、よくよく考えてみると、間のステップがいくつか抜けているだけで、中身は意外と筋が通っている。その抜けたステップを補いながら一緒に構想できる人にとっては、面白さを感じてもらえているんじゃないかと思います。
杉森氏の隣で笑いながら相槌を打つ代表の佐々木氏は、たしかに独特のオーラを持つ人物だ。話した相手瞬時に虜にしまうような、“人たらしの才能”とでも言うべき魅力を持っている印象を受けた。そんな人格を形作った背景について彼は、「本当はすごくビビっているんですよ」と照れ笑いながら口を開く。
佐々木
よく組織では「事業とは破壊と再生」と言いますけど、僕はこの10年間の間に、会社が自然にぶっ壊れた瞬間を2回見ているんですよ。
そう、Fabeeeを創業してからの11年間の歩みは、決して順風満帆なものではなかった。普通ならもう諦めてしまいたくなるような大きな挫折を何度も乗り越えて、ようやく今の安定的な事業体制を築き上げてきたのである。次のセクションからは、佐々木氏が企業に至るまでの経緯と、事業の軌跡を振り返る。SECTION2/4
起業家志望の小学生が、「IT」に目覚めるまで
佐々木氏は大学を卒業後、不動産を扱う会社で営業を経験。その後2社目で人材紹介の会社に入社し、独立・起業というキャリアパスを経ている。一見つながりのないようにも見えるこの経歴に対して、「そもそもなぜ起業しようと思ったのか」という質問を投げかけると、こんな答えが返ってきた──「起業家になることは、小学生の頃から決めていました」。
佐々木
僕はけっこうなおばあちゃん子だったんですが、その祖母がブティックを何店舗か経営していました。母親がお店の手伝いをしていたこともあり、物を仕入れて売る、お会計をしてお客さんに商品を渡す、といった“ビジネス”が日常のとても身近なところにあったんです。ですから自分も、「将来は自分で事業をやりたい」と、その時から自然に思っていました。
しかしその後サッカーに出会い、高校3年生までひたすらサッカー漬けの日々を送ったという。
起業や経営に対して、再び関心が向きはじめたのは、大学に入ってからだ。当時仲の良かった先輩の父親がコンサルティング会社を経営しており、その仕事を手伝わせてもらう中で、さまざまなビジネスを“裏側”から見る経験をしたという。
佐々木
コンサルに入っている清掃会社の課題を探るため、閉園後の大手テーマパークに行って清掃をしたり、上場前の有名メディア企業に行って、そこで朝まで働いている人にインタビューしてみたりと、普通はなかなかできないような経験をさせてもらいました。いろんなビジネスの現場に直に触れるうちに、自分ももう一度起業の道を目指したい気持ちが湧いてきたんです。
起業を目指すにあたっては、「大きなお金が動くマーケットを見た方が良いよ」とアドバイスを受け、新卒では金融業界と不動産業界を志望。晴れて不動産会社の営業職に就くと、「3年以内にトップ営業マンになる」と目標を立てた。
佐々木
2年10ヶ月目で、無事トップの営業成績を残せたので、すみやかに辞表を出して退職しました。次の会社も決まっていない状態で、です。そして次は「経営のことを知りたい」と思い、経営コンサルティングの会社をひたすら受けました。
そうして内定した会社のうちの1つが、人材コンサルティングの会社だった。面接官だった部長の「次の会社に行った後でも良い、ずっと待っているから」という言葉に胸を打たれ、入社を決めたという。
独立の転機が訪れたのは、IT業界向け人材紹介事業の立ち上げを任されたときのことだ。日々IT業界の転職志望者と関わる中で、「IT業界は面白い、めちゃくちゃすごい人たちがいる」と、俄然興味を惹かれた。
それと同時に、本当はIT業界のことをほとんど何も知らないにもかかわらず、知ったかぶりで転職志望者に求人紹介をしている自分に「ほとほと嫌気が差した」という。「自分の力で成果を出してこの“ダサさ”を何とかしよう」と独立を決意した。
中国での“ソースコード丸パクリ事件”、業界団体からの圧力……波乱万丈の起業家人生
独立を果たした後、最初に着手したのは「フォトメ」という、昨今のInstagramと類似した写真ウェブサービス事業の立ち上げだ。会社名もサービス名と同じ「フォトメ」で、2010年4月に会社を設立した。
佐々木
独立しようかと右往左往していた時期、転職志望者の一人で、大手外食チェーンのクリエイティブディレクターも務めたフォトグラファーの方がいたんです。その方と独立についてディスカッションするうちに、「俺がサポートしてやるから今起業しろ」と背中を押され、起業に踏み切りました。
「フォトメ」という事業に対して抱いていたのは、「言語がわからなくても、世界中の人がつながれるようなコミュニティを作りたい」という想いです。たとえるなら、ディズニーランドの「イッツ・ア・スモールワールド」のような世界観ですね。
それまでずっと「起業すること」をゴールに、自分のエゴをモチベーションにして突き進んできたんですが、この頃から「社会に価値を提供したい」という方向に変わってきました。
Instagramのサービス開始が2010年10月であるから、この「フォトメ」の構想はちょうど時代を先取りしていたと言える。しかしながら結論から言えば、この最初の事業は大失敗。サービスをリリースすることすら叶わなかった。
佐々木
いきなり中国に行ってしまったのが、全ての間違いでした。今だったら絶対にそんな選択はしないんですけど、当時は妙にグローバル志向だったんですよね。
その時ほとんど運命的なタイミングで中国の国営企業の社長さんと知り合うことができて、その人のツテをたどって中国の湖南省に渡りました。現地の会社とジョイントベンチャーを作って、中国でサービスを展開しようと考えたんです。
中国に渡った佐々木氏は、ありとあらゆるものの日本とのスケールの違いに圧倒された。加えて中国は「スタジオでコスプレをして撮影し、額に入れて家に飾る」という文化が生まれはじめたタイミングであり、大きなチャンスを感じたという。
佐々木
日本ではすでに、スタジオで写真を撮影するような文化は成熟しきっていました。一方で中国はこれから、しかも日本とは比べ物にならないような規模で市場が成長していくというタイミング。このギャップを埋めていく作業が楽しくて、ワクワクが止まりませんでした。「中国で活躍した、フォトメの佐々木が帰ってきた!」と言われるようなマーケットを作りたいとか、妄想していましたね(笑)。
ところが中国には、日本とは比べ物にならない大きさのマーケットがある一方で、日本では考えられないようなリスクも潜んでいる。唐突に法律が改正されることをはじめ、自国ではあり得ないような中国独自の文化に翻弄される──俗に言う“チャイナリスク”というやつだ。佐々木氏もまたご多分に漏れず、リリース直前というタイミングで“まさかの事態”に直面することとなる。
佐々木
プロトタイプもできて、「後はデザインを入れるだけ」というタイミングで、パートナーであった企業との折り合いが付かなくなりました。日本で生まれ育った私としては、全く想定していなかった、“コピー問題”に直面したのです。現地のお作法を知らないままに飛び込んでいたことで、結局事業は白紙になりました。「やりたいことを実現できなかった」という強烈な悔しさがありましたね。
何の成果も残せず日本に帰ることを余儀なくされた佐々木氏は、当座の運転資金を得るべく、企業向けのエンジニア派遣事業を開始した。しかし、「モノを作って世の中に一石を投じたい」という想いは消えることなく、2014年に『Footi Stream』というスポーツ動画キュレーションアプリをリリースした。
佐々木
自分のバックグラウンドはスポーツにあったので、今度はスポーツを切り口に事業を着想しました。リリースしたアプリは1ヶ月間で10万近くダウンロードされ、レビューもかなりの高評価で、手応えを感じました。「これは行けるんじゃないか?」と思いましたね。
ところがこの2つ目の自社事業も、思わぬ形で頓挫する。スポーツ業界でビジネスを展開するうえでの“お作法”を知らなかったため、サービス停止に至ったのだ。
佐々木
既にプレイヤーが確立している成立している市場に、新しいビジネスモデルを持ち込んだ結果、身動きを取りづらくなってしまいました。自分たちにとって新しい環境で何かを成すためには、事前調査が非常に大切だと学びました。コトをはじめること自体が成功ではなく、形にして維持していくまでが必要なのだと。
ビジネスには、いつだって想定外のトラブルがつきものだ。自分にはどうにもならない力によって、こうして事業が頓挫してしまうこともある。しかしながら、大きな挫折を二度味わってもなお、佐々木氏は次なる挑戦に向けた姿勢を崩さない。むしろ10年分の悔しさを溜めたその目の光は、いっそう力強く灯っている。
佐々木
世の中に自分で構想したプロダクトを出して、それを皆が使ってくれて、対価をいただく──創業当時からずっと夢見ていたことが、この10年間で一度も実現できていないんですよ。そのことが悔しくて、悔しくて。自分の人生、なんでこんなに遠回りするんだろうって、考え続ける10年でした。
でも、2020年代に突入したいま、ようやくプロダクトを世に送り出す段階に来ました。強いビジョンを持ち、それを現実世界のニーズと符合させることの重要性を学び、実行したからです。諦めない限り、点と点はつながる。“目の前のにんじん”だけが目指すものとは限らず、愚直にやり続けていくプロセスの中に、自分が実現したいことのヒントがあるんです。さまざまな失敗を一通り経験してきたので、今度こそビジョンの実現に向かって真っ直ぐ進んでいきます。
「非エンジニアでも、システムと対話するだけでプログラムが作れる」世界を実現する
挫折と忍耐の季節を経て、第二創業へ向け大きな一歩を踏み出したFabeee。これから手始めに取り組むのは、社内向けのローコード・ノーコードのプラットフォーム開発だ。
佐々木
目指しているのは、エンジニアではない僕のような人間が、システムと対話するだけでプログラムを作れる世界です。非エンジニアがクリエイティブな思考を持って、エンジンに話しかけて、それがプログラムとして生成できたら、オンラインとオフラインの境界が1つ無くなりますよね。
そのためのファーストステップとして、ローコードと呼ばれる、今までは100%自分で書かなければいけなかったコードを30%くらいの労力で書けるような仕組みの開発に、全社として取り組んでいます。
また、具体的にローコード・ノーコードのプラットフォームを開発する手法について、杉森氏は次のように補足する。
杉森
クライアントからあるシステムについて開発の依頼を受けた後に、また別の会社から似たようなシステムの開発を依頼されるケースがありますが、その際それぞれのコードに、被る部分が必ず発生すると思います。
であれば、その「被る部分」とはどこなのか。次の開発の際に、簡単に使いやすくする方法はないのか。それらを突き詰めていけば、最小限のコードでクライアントが実現したいことを実現できる。これが、僕らの考えるローコードの概念です。世の中で一般にローコード・ノーコードと呼ばれているものとは、少し異なるとは思います。
この方法でローコード・ノーコードのプラットフォームを作るためには、システムやコードに関する大量のデータを収集していく必要がある。そのため今後は「ALICE」と名付けた、独自のデータ収集フレームワークを使って、DX支援事業で発生した知見を蓄積していくという。
また、この社内向けプラットフォームは、いずれSaaSなどのプロダクトとして一般展開する構想だと語る。来期以降Fabeeeは、ローコード・ノーコードのプラットフォーム開発への注力とIPOを見据えた体制強化のため、採用にも力を入れていくという。
杉森
ローコード・ノーコードって、やっぱり面白い仕組みだと思うんですよね。設計書さえあればシステムが出来るというのは、エンジニアにとっての夢でもあるというか。もちろん「それができちゃったらエンジニアの仕事が無くなっちゃうじゃん」と考える人もいると思うのですが、そうした矛盾についてのディスカッションも含めて、実際に作っていくことができるのは魅力に感じます。
「何かをやりたい」と言った時にすぐにそれが全員に伝わって、「面白いね!」と自然に賛同し、さまざまな視点からアイデアをくれるメンバーがいる点はFabeeeの魅力だと思います。とにかく、メンバーを巻き込みやすい。主体的に何かに取り組みたいと思っている人にとっては、すごく良い環境でしょう。うちには稟議はありませんから。「やりたい」と思ったらまずやってみて、上手く行かなかった点については、後から考えればいいというスタンスです。
佐々木
サントリー創業者の「やってみなはれ」という格言がありますが、まさにそのような精神です。メンバーの「やりたい」という気持ちを尊重する文化は常に大切にしていて、「オンラインとオフラインの境界線のない世界」につながるものであれば、「NO」と言うメンバーは誰もいません。このビジョンに共感してくれる方がいたら、ぜひ一緒に未来を作りましょう。
これまで数々の失敗を経験してきたからこそ、挑戦を恐れず、どんな失敗も明日の糧にしていく文化がFabeeeにはある。他の会社なら「デカすぎる」と笑われるであろう壮大なビジョンを、一緒に目指せる仲間もいる。
もし、あなたのどこかに「SF映画の世界を、自分の手で実現できたらな」というキラキラした夢が眠っているなら、勇気を出してFabeeeの扉を叩いてみて欲しい。